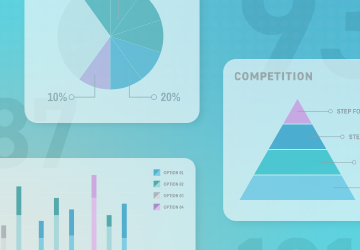アメリカの若年成人を対象にした30年間の追跡調査でマグネシウム摂取量が多いと肥満リスクが低くなる可能性
最終更新日時 : 2025.10.29

2020年、米国のコロンビア大学アービング医療センター、メールマン公衆衛生大学院、中国・上海交通大学医学部、テキサス州立大学、インディアナ大学、アラバマ大学医学部などの共同研究チームは、
「アメリカの若年成人を約30年間追跡した研究において、マグネシウム摂取量が多い人ほど肥満のリスクが低い傾向がある」と報告しました。
以下では、その研究概要をご紹介します。
Lu L, Chen C, Yang K, Zhu J, Xun P, Shikany JM, He K. Magnesium intake is inversely associated with risk of obesity in a 30-year prospective follow-up study among American young adults. Eur J Nutr 59: 3745–3753, 2020
doi:10.1007/s00394-020-02206-3
詳しくはこちら
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7483156/
背景
- マグネシウム(Mg)は、実験レベルでは体重や代謝の調節に関与する可能性が示唆されていましたが、ヒトを対象とした長期的な研究は限られていました。
- 本研究では、米国若年成人集団を約30年間追跡し、食事からのMg摂取量と「肥満(BMI ≥ 30 kg/m²)」の発症および体格・生化学マーカーとの関連を検証しています。
方法
- 試験対象:米国の若年成人 5,115名(1985-86年時点、年齢18~30歳)を起点に、8回の追跡。
- Mg摂取量の評価:ベースライン+7年後+20年後の食事履歴から。
- 肥満定義:BMI ≥ 30 kg/m²。追跡期間中に発症した “新たな” 肥満(incident obesity)として分析。
- 統計調整:年齢、性別、人種、エネルギー摂取量、喫煙、運動、飲酒、その他食事因子など。
主な結果
- 追跡期間中に1,675名が肥満を発症。
- Mg摂取量を五分位(Q1=最少〜Q5=最多)に分けたところ、Q5(最も多くMgを摂取)群の肥満発症ハザード比 (HR) はQ1群と比較して 約0.49(95% CI: 0.40-0.60)という強い逆関連が認められた。P-trend < 0.01。
- また、Mg摂取量が多いほど、BMI・上腕三頭筋スキンフォールド・肩甲下・上腸骨部スキンフォールド(体脂肪指標)・空腹時インスリン・C反応性蛋白(CRP:炎症マーカー)が低めという関連も観察されました。
- この関連性は、年齢・性別・人種・ベースラインBMIによって大きく変わるものではなかったという報告です。
- 飲食パターンとして、Mgを多く含む食品(全粒穀物・ナッツ・種子・豆類・濃色葉野菜)の摂取も、肥満発症リスク低下と関連していました。
考察・意義
- 著者らは、「食事からのMg摂取が多いほど、肥満を新たに発症するリスクが低くなる可能性がある」としており、Mgの体重制御・脂肪蓄積・代謝異常に対する潜在的役割を示唆しています。
- 作用機序として、Mgがエネルギー代謝(ATP代謝、酵素活性)、脂肪酸の腸管内吸収抑制、インスリン抵抗性・慢性炎症の改善といった複数の経路を通じて影響を及ぼしうる可能性が解説されています。
留意点・限界
- 観察研究(前向きコホート)であり、因果関係を確定するものではありません。
- 食事調査が自己申告型であるため、摂取量の誤差・交絡因子の影響の可能性があります。
- 米国の若年成人(開始時18-30歳)を対象としており、日本人/中高年/高齢者など他集団への一般化には慎重を要します。
- 「Mg摂取=肥満にならない」という単純な構図ではなく、他の栄養素・生活習慣・遺伝など複合的要因が関与します。