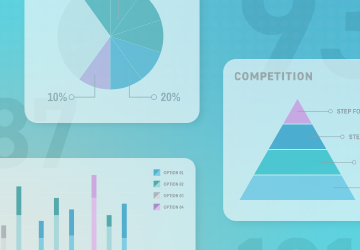心の安定を助けるマグネシウムのストレスを抑制する効果
私たちの体の中に常に存在し、様々な生命活動を助けてくれているミネラル。その中でも、心身の健康のために必要不可欠なものの1つが「マグネシウム」です。
マグネシウムはあまり注目されることは少ないイメージですが、実は“天然の精神安定剤”と呼ばれ、心の安定に良い効果を発揮することが分かってきて注目を集めているミネラルなのです。
そんなマグネシウムは、現代の食の欧米化やストレスなどの影響で、多くの人が不足しがちな栄養素。マグネシウム不足が招く体の不調にはどんなものがあるのでしょうか。
マグネシウムとストレスに焦点を当てて解説していきます。
マグネシウムとストレスの関係とは?

マグネシウムは、私たちの体の中で7番目に多い必須ミネラル。様々な体内酵素の正しい働きとエネルギーの生産を補助し、血液循環も正常に保つ重要な栄養素です。そんなマグネシウムはメンタルにも大きく影響を及ぼします。
マグネシウムは、心を安定させてくれる神経伝達物質「GABA」、“幸せホルモン”と呼ばれることで知られる「セロトニン」の分泌を促す働きを持っています。GABAとセロトニンが多く分泌されることで、緊張感や心の不安感を和らげることで、ストレスを抑制してくれます。
一方で、私たちはストレスと感じると、副腎から「コルチゾール」「アドレナリン」というストレスホルモンが分泌されます。
このストレスホルモンは、マグネシウムの排出を促してしまう働きがあり、マグネシウム不足を招きます。不足することでGABA・セロトニンの分泌が減少し、ストレスに弱くなる…という悪循環に陥ってしまいます。
マグネシウムが心身のバランスに与える役割
マグネシウムは、体内のミネラルバランスを整えてくれる重要な栄養素で、私たちが心身共に健康に過ごすために必要不可欠です。様々な神経細胞への情報伝達を担っており、機能維持のために今この瞬間も私たちの体の中で働いてくれています。
主な働きとしては、「筋肉の働きを調整」「神経の興奮を鎮める」「骨の形成を助ける」「動脈硬化を予防・治療する」「心機能を維持する」などが挙げられますが、最近では高血圧や糖質代謝との関係も研究されており、その役割は多岐にわたります。
ストレス反応におけるマグネシウムの働き
最近では、うつ病の治療薬としても使用されるほど抗ストレス作用に注目されているマグネシウム。ストレスを感じた時に、マグネシウムは私たちの体の中でどんな働きをしているのでしょうか?
ストレスを感じると、副腎皮質からストレスホルモンである「コルチゾール」が急激に分泌を開始します。コルチゾールは、血糖値を上げたり、タンパク質の代謝の促進、抗炎症作用があるなど生命維持に欠かせないホルモンの1つです。しかし、過剰に分泌されることで脳の働きを鈍らせ、感情のコントロールができなくなるという状態を引き起こします。さらに、精神を安定させる働きがあるセロトニンの分泌を抑制してしまう作用もあるため、心身共に疲労状態となってしまいます。
マグネシウムには、コルチゾールの分泌を抑制しセロトニンの分泌を促す働きがあるため、イライラを鎮め不安感や緊張を軽減することができるのです。
ストレスが引き起こす健康への影響

ストレスは「万病の元」と言われており、心身の健康に様々な不調をきたす原因となることがあります。総理府の調査によると、半数以上の人が何かしらのストレスを抱えているという報告があります。自覚がなくても実は大きなストレスを抱えていたという方もいらっしゃるでしょう。目に見えないストレスは、気づかないうちに負担となり心身をむしばんでいるかもしれないのです。
原因不明で長く悩んでいた不調の原因が、実はストレスだった…ということも少なくありません。
ただ、すべてのストレスが良くないというわけではなく、適度にかかるものであれば乗り越えた達成感から自信に繋がり、成長の糧になることもあります。どう上手く付き合っていくかが重要です。
長期的なストレスが体に与えるダメージ
では、長期的にストレスがかかった場合、具体的にどんな不調が現れるのでしょうか。
- 頭痛、肩こり、背中の痛みなど
- 動悸・息切れ
- めまい
- 胃腸の不調(下痢・便秘・吐き気など)
- 免疫力の低下(風邪やインフルエンザなどにかかりやすくなる)
- 高血圧
- 不安やイライラ
- 気分の落ち込み
- 不眠
- うつ病などの精神疾患
- アルコールやギャンブルなどへの依存
- 暴力
上記以外にも挙げきれないほどの心身への影響があるのが現実です。ストレスに対する体の反応は複雑で、明らかになっていないことが多くあります。症状を全体的に改善できるような薬は開発されていないため、「溜め込まない」ということが一番の薬です。
不眠症や疲労感への影響とそのメカニズム
特に若年層に多い不眠の原因にストレスが挙げられます。
悩みや心配事が夜まで持続してしまうと、神経が高ぶり寝つきが悪くなることがあります。そして一度寝つけない経験をすると「また今日も眠れないかも…」という不安からさらに寝つけなくなる、不眠恐怖という状態を招きます。
また、ストレスがかかることで、ノンレム睡眠が減少しレム睡眠が増加してしまうため途中覚醒も起こります。
このように十分に睡眠がとれないことで、日中に疲労感や倦怠感が起こり日常生活に支障をきたす状態が「不眠症」です。
ただ、必要な睡眠時間は人により違うため、ショートスリープであっても日中元気に過ごせる場合は不眠症ではありません。
マグネシウムがストレスを抑える科学的根拠

元国立健康・栄養研究所の西牟田守先生が過去に行った、ストレスと栄養素の喪失の関係についての実験報告があります。
- コールドルームで過ごし肉体へストレスをかける
- 長時間単純な計算ドリルを行い精神へストレスをかける
- 目隠しをして座り話をせず長時間過ごし情動へストレスをかける
上記ストレスをかけた日とかけない日で、尿中に排泄されるミネラル量を比較した実験結果では、肉体・精神へのストレスをかけた際、マグネシウムの尿中排泄量が増えたという結果が出ています。
心身の健康のために重要な役割を持つマグネシウムが喪失してしまうことで、心身の不調を招くことがあるのです。
神経伝達物質やホルモンとの相互作用
マグネシウムは、体の中で300種類以上もの酵素反応に関わる必須ミネラルで、私たちの健康を維持していくのに重要な働きをしています。その中でも神経伝達物質にも大きく関わっており、マグネシウムが体内で充足していてきちんと働いてくれることで健やかに過ごすことができるのです。
神経をリラックスさせ、ストレスを和らげてくれるGABAやセロトニンの分泌を助けるほか、メラトニンの生成もサポートしています。メラトニンは安眠ホルモンとして有名で、睡眠・覚醒のリズム、ホルモン分泌のリズムのような概日リズムを調整してくれる作用があります。睡眠の質が向上することで疲れを癒し、日々のパフォーマンスが良いものになりますね。
また、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑えられるため、ストレス耐性のある体づくりを目指すことも可能です。
マグネシウム不足がもたらす症状

多くの方が十分に摂取できていないとされるマグネシウム。普段の生活の中で不足していることに気づきにくく、分かりやすい症状などもありません。
マグネシウム不足が進行すると、どんな症状が出るのでしょうか。
- 筋肉・神経系に関わる症状 こむらがえりや痙攣、疲労感、筋力低下、手足のしびれ
- 精神に関わる症状 うつ症状、記憶力・集中力の低下、イライラや不安
- 睡眠障害 寝つきが悪い、夜中に何度も覚醒する、熟睡できない
- 循環器系の症状 動悸や不整脈、血圧の上昇
- 消化器系の症状 便秘、胃の不快症状、消化不良
- 骨に関わる症状 骨粗しょう症、骨軟化症、歯のエナメル質の弱化
その他にも挙げきれないほどの影響があります。それほど、マグネシウムが私たちの心身にとって重要な働きを持っているということです。
不足時に起こるストレス悪化や疲労感
前述したとおり、体内のマグネシウムが不足すると心身に様々な問題が起こります。近年神経系への大きな影響が分かってきており、不足すると神経伝達物質である「ドーパミン」の分泌が減ってしまいます。
ドーパミンはやる気や集中力などに関与するホルモンで、セロトニン・エンドルフィンと並び「3大幸せホルモン」と呼ばれています。このドーパミンが減少することでセロトニンの分泌も減少してしまうため、不安やイライラなどのストレスを感じやすくなってしまうのです。
また、ドーパミンは運動機能にも関与しているため、不足すると身体に疲労感が溜まりやすくなります。マグネシウム自体にも筋肉やエネルギー代謝に関わる働きがあるため、マグネシウムが不足することで疲労感を感じやすくなると言えます。
日常生活で注意すべきサインとは
日本人の約7割が推奨量を下回ると言われる摂取量のマグネシウムですが、初期段階で不調のサインに気づくことはできるのでしょうか。
- 足がつる(こむら返り)
- 目の周りがぴくぴく痙攣する
- 首・肩のこり
- 片頭痛
- 疲れやすい
- やる気が出ない
- 眠りが浅い
こんな体調の変化があらわれたら、マグネシウム不足のサインかもしれません。これらの症状は、日常生活の中で「ちょっと最近疲れてるのかな…」程度で見過ごされがちですが、長期的にこんな症状が続く場合は注意が必要です。大きな病気に進行してしまう前に、食事や生活習慣を見直して健康的な日常を手にいれましょう。
マグネシウムで心の安定を手に入れよう
マグネシウムとストレスの関係について解説してきましたが、マグネシウムの摂取を意識することで、体の内側からストレスに打ち勝つ体に変えていく方法もあるということを意識してみてください。
食生活の欧米化や薬剤の服用などの原因で不足しがちなマグネシウム。毎日の食事と生活習慣を変えてみることと、適切なサプリメントを摂取することで不足を防ぎたいものです。
大切な体のことを考え、なるべく自然な状態に近い高品質な“飲むマグネシウム”の天然濃縮ミネラル液「高濃度マグネシウムNatureMineral」は、飲料はもちろん料理にも使用することができ、高濃度なマグネシウムを安心して手軽に摂取することが可能です。
知ること、そして行動することで良い方向へ自分を変えていくことができます。
一度試してみてはいかがでしょうか。