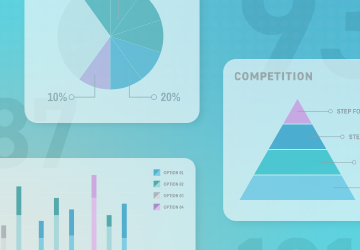糖尿病の発症リスクや合併症とマグネシウム摂取の有用性
知ることが予防の始まり!糖尿病の発症リスクを詳しく知ろう

皆さんはどれぐらい糖尿病についてご存じでしょうか?
糖尿病の特徴を最初にふれておきます。糖尿病は「サイレントキラー」とも言われて、ほとんど自覚症状がありません。そのため、多少血糖値が高いぐらいではほとんどの人は気付きません。
逆に、糖尿病の症状がではじめたときには、糖尿病が既に進行してしまっている状態であったり、悪化している状態という可能性が考えられます。
従って、症状が出てからでは遅いので、きちんと糖尿病について知ることから始めましょう。そして、発症リスクについてしっかりと理解して予防できることは予防するようにしていきましょう。また、厚生労働省の「令和元年国民健康・栄養調査」によれば、疾患が疑われる人を含めると、日本人の5~6人がり患しているといわれているので、自分事として考えておくことが必要です。
糖尿病と遺伝の関係性
糖尿病は遺伝するといわれています。過去の調査によると、兄弟姉妹が2型糖尿病にかかっている場合はは2-3倍、両親が2型糖尿病患者の場合は3-4倍発症します。従って、家族に糖尿病患者がいる場合はリスクが高いのでより注意する必要があります。
糖尿病と肥満の関係性
肥満の人は標準体重の人と比較すると、2型糖尿病を発症するリスクが6倍以上高いといわれています。これは、血糖値を下げる働きをする「インスリン」が肥満になるとにぶくなるため、すい臓がインスリンをたくさん作ろうとして体内のインスリン量が増加しますが、やがてすい臓が疲れて機能が低下して血糖値が上がり始める、といったことからも、リスクが高くなることがわかります。
肥満の定義は、BMIが25以上です。BMIの計算は(体重kg÷身長m÷身長m=BMI)です。身長の単位がmであるところに気を付けましょう。計算機があれば簡単に計算できるので、ご自分のBMIを確認しておきましょう。
糖尿病と年齢の関係性
厚生労働省の「患者調査」によると、若い世代には少なく、50歳代以上、特に60歳代以上で多くなっています。つまり、年齢とともにリスクが高まっていることがわかります。
糖尿病と血管の関係性
血糖値が高い状態が長く続くと、血管が傷んでしまいます。そのため、糖尿病が原因となって血管病にかかるリスクがあります。全身の血管が傷つくことから、目の網膜症であったり、足の壊疽であったり、と全身の合併症をひきおこす可能性があります。
糖尿病よりも怖い”三大合併症”とは?

糖尿病の三大合併症についてついて解説します。この三大合併症はきのこの”しめじ”で覚えておきましょう。”し・め・じ”の”し”は、神経の障害の”し”です。”め”は網膜症が目の障害なので”め”です。”じ”は腎臓の障害の”じ”です。何かの試験勉強のようですが、看護学生は看護師国家試験のためにこのゴロあわせで覚えたりします。
そして、このしめじの順番で障害が起こりやすいです。腎臓の合併症の症状が出てから治療を始めても改善しないことが多いため、その前に予防・対策しておくことが望ましいです。
この三大合併症の結果として、足の切断・失明・腎機能低下で人工透析が必要になる、最悪の場合は死亡してまう、といったことがあり、恐ろしい病気です。
糖尿病神経障害とは?
糖尿病神経障害とは、私たちが物に触れて感じる”感覚神経”、手・足を動かす”運動神経”、血圧のコントロールや消化管を動かす”自律神経”といった、神経の障害です。原因として、血糖値が高い事による神経細胞の変化であったり、動脈硬化からくる神経細胞への血流不足が考えられます。
これらの障害がおきていた場合の例として、足をぶつけて出血するほどのケガをしていたのに”痛みがない”ので気づかないということがあります。そして、辛い症状がないので病院に行かずに様子をみていたところ、傷口からばい菌が入って化膿して感染が広がり、足を切断しなければならなくなる、ということがあり、非常に恐ろしい病気であることがわかります。
神経障害による異常は多数あります。感覚の異常、胃腸運動の異常、心臓や血圧調節の異常、四肢の異常、目や顔面の異常、泌尿器・生殖器系の異常、発汗障害、血糖コントロールに影響する異常があげられます。血糖値が高めでこれらの異常を感じた場合は、まずは病院で診察してもらいましょう。
糖尿病網膜症って何?
糖尿病網膜症とは、糖尿病が原因となって目の中の網膜が障害を受けて視力が下がる病気です。網膜とは、目の中に入ってきた光を刺激として受け、視神経に伝達する組織です。
糖尿病網膜症の症状は、初期では自覚症状がみられません。しかし、目の中の血管には小さな出血などの異常があります。中期になると、視界がかすむ等の症状が感じられます。目の中の血管が詰まる等の異常があります。末期になると、視力低下や飛蚊症がおこり失明になることもあります。目の中で大きな出血がおきていたり、網膜剥離や緑内障などの他の病気を併発している場合もあります。
糖尿病網膜症は、糖尿病が進行して網膜にある細い血管がダメージをうけるといったことが原因となります。先に述べたように、初期では自覚症状がみられませんが、糖尿病を放置しておくとどんどん進行して、最悪の場合、失明になってしまう病気です。糖尿病と診断された人は、眼科を定期的に受診するようにしましょう。
糖尿病腎症って何?
糖尿病腎症とは、血糖値が高い状態が長く続いたことにより腎臓が傷んでしまい、腎機能が低下してしまう病気です。
腎臓のはたらきは、血液をろ過して尿をつくったり、体液のバランスを保ったり、ホルモンを作る、といったはたらきがあります。つまり、糖尿病腎症のなるとこれらのはたらきが低下してくることになります。
糖尿病腎症は第1期から第5期まで病気が分けられており、初期の第1期・2期では自覚症状がみられませんが、第4期には倦怠感、全身のむくみ、手足のしびれなどの症状がでてきます。第5期まで進行すると人工透析を受けなければならなくなってしまいます。人工透析の血液透析は、体から血液を取り出し、透析器できれいにした血液を再び体に戻す方法になります。1回4~5時間、週に数回、通院する必要があります。糖尿病腎症を治せる薬がないため、血糖コントロールをしっかりおこなって、進行を防ぐことが大切になってきます。
命に関わる糖尿病の急性合併症とは

糖尿病の急性合併症は命に関わる危険があります。急性合併症として糖尿病昏睡(高血糖昏睡)、急性感染症、低血糖があげられます。
- 糖尿病昏睡(高血糖昏睡)
糖尿病昏睡(高血糖昏睡)とは、インスリン作用が極端に不足したときに生じる高血糖に伴う意識障害をいいます。インスリン注射をやらなければならないのにやめてしまったり、感染症にかかったり、ストレス、過労、暴飲暴食が発症の原因となります。全身の倦怠感、口の渇き、多尿、眠気、吐き気・嘔吐、腹痛、意識障害などの症状があります。インスリン静脈注射、輸液、電解質補正などによる治療を行います。糖尿病昏睡(高血糖昏睡)を予防するためには、普段から血糖値のコントロールを行って数値を良好に保つ、感染症を十分に治療する、勝手な判断でインスリン注射をやめないことが大切になります。
- 急性感染症
糖尿病になると、細菌やウイルスなどに対する体の抵抗力が弱くなります。そのため、かぜ、膀胱炎、皮膚炎などの様々な感染症を起こしやすくなります。予防には血糖値のコントロールと規則正しい生活が大事になります。感染症には抗菌薬による治療を行います。
- 低血糖
低血糖とは、血糖値が正常範囲以下にまで下がった状態になります。低血糖を放置することは危険で昏睡に陥ることがあります。インスリンや経口血糖降下薬が多すぎたり、食事時間が不規則だったり、ダイエット等で食事量を少なくしている場合などに起こります。血糖値に応じて様々な症状がでてきて、悪化が進むと意識がもうろうとし、けいれん、昏睡になります。自分で気づいた場合には、砂糖15-20gや糖分を含むジュース等を摂取します。意識がない場合には、家族や周囲の協力が必要になってきます。砂糖・ブドウ糖を歯茎と唇の間に擦り込んだり、肝臓のグリコーゲンを分解して、ブドウ糖を放出する作用があるグルカゴン注射が、処方されていれば注射します。予防には、規則正しい食事、適度な運動、糖分の携帯を行います。
糖尿病の進行ステージによって異なる症状を詳しく解説
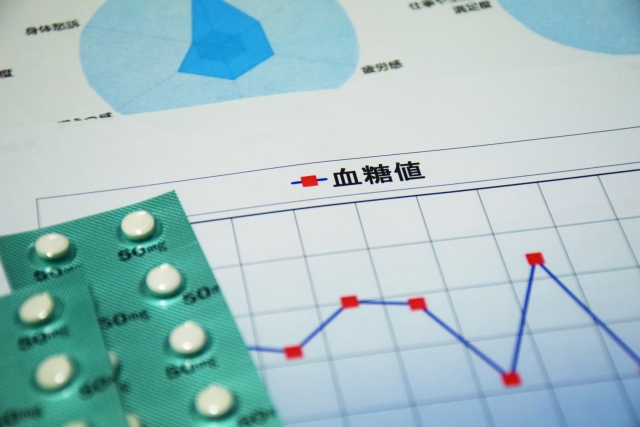
自覚症状がでにくい病気ではありますが、症状がでる場合もあります。糖尿病の進行ステージによって症状は異なってきますので、解説していきます。
足に表れる糖尿病の初期症状
足のしびれは糖尿病の初期症状の1つです。足の神経障害で痺れがでる、指先が冷えて徐々に足の感覚がなくなる、水虫・小さな傷からばい菌が入って足が腐り切断しなければならない、ということがあります。
糖尿病 むくみ
足のむくみは合併症の糖尿病性腎症が進行し、腎不全になって出てきている症状です。
尿に表れる糖尿病の初期症状
多尿も糖尿病の初期症状の1つです。これは、糖尿病によって血液の中に糖がたくさんあるため、その濃度を下げようとして体が水を欲します。そのことによって、多尿につながります。多尿とは1日の尿量が3リットル以上のことをいいます。そのため、糖尿病の人の尿はほぼ透明であることが多いです。他に、尿のにおいは糖尿病でなくても食べ物の影響を受けるので一概にはいえませんが、糖尿病の人の尿はブドウ糖が多く含まれるため、甘くて独特のにおいがします。
泡
合併症の糖尿病腎症が進行すると、尿中に糖やタンパク質が多く混ざるため泡立ちます。健康な方の尿でも泡立つことがありますが、この泡はすぐに消えます。しかし、タンパク質の混ざった尿の泡立ちは短時間で泡は消えませんので、こういった泡がでてきたら注意しましょう。
排尿障害
合併症の糖尿病神経障害による異常として排尿障害があります。骨盤にある膀胱に働きには自律神経が関わっていて、この機能障害によって排尿困難や残尿感、尿閉(尿が出せなくなる状態)になってしまいます。
糖尿病の喉に表れる初期症状
前述したように糖尿病によって多尿の初期症状があります。これによって、体の水分がなくなっていくため、喉が渇く症状がでてきます。
糖尿病 吐き気
糖尿病急性合併症である糖尿病昏睡のひとつの糖尿病ケトアシドーシス症状で、のどの渇きや多尿、体がだるくなったりといった症状に引き続いて急激に発症し、悪化すると吐き気や嘔吐といった症状がでます。吐き気の症状が出てきた場合は急激な高血糖をきたしている可能性があります。
喉の渇き
夏の暑い日や運動の時に汗をかいたりした時に喉の渇きを感じたことがあるでしょうか?ある程度水分を補給すれば喉の渇きはおさまりますよね。しかし、糖尿病の場合は、いくら飲んでものどやたらと喉の渇きがおさまらない場合もあります。高血糖による多尿で水分がでていくため体が脱水症状になって喉が渇いてきます。喉が渇くので水を飲みますが、血糖値を下げなければ摂取した水は尿として水分が出ていってしまうので、喉の渇きがおさまらないのです。
糖尿病の末期症状
糖尿病合併症が進むと血糖値を下げても症状の改善が難しくなってきます。末期症状とは、すでに手の施しようがない症状のことをいいます。三大合併症ごとに末期症状をみていきましょう。
- 糖尿病神経障害
怪我が治りにくくなったり、手足の感覚がなくなったりしていき、体の細胞が死に最終的には腐ってしまう壊疽(えそ)と呼ばれる状態になってしまいます。壊疽になると、腐った部分を切り落とすしかなくなります。
- 糖尿病網膜症
見えにくくなっていた目が末期には失明してしまいます。
- 糖尿病腎症
腎臓は機能しなくなってしまうため人工透析が必要な体になります。
糖尿病 急死
糖尿病によって動脈の壁が硬くなる動脈硬化が起こります。動脈硬化になると血液の流れる部分が狭くなり、血液が流れにくくなります。そして、この動脈硬化をきっかけとして、脳梗塞や心筋梗塞などを引き起こし急死してしまうことがあります。
糖尿病ともう一つの症状”脂質代謝障害”を詳しく解説

糖尿病の人は脂質代謝障害の症状がでる確率が高いです。そして、脂質代謝障害の症状がでる脂質異常症になった糖尿病の人は心臓病などになる危険が高いといわれています。脂質は全て体に悪いというような印象を持っている方もいるかもしれませんが、血液中の脂質は細胞膜を作るために必要になったり、ホルモンの材料になったり、エネルギーを蓄えるなど、体の機能を保つために大切な働きをしています。
通常、脂質は肝臓で作られたり、食事から取り込むことで、血液中に一定の量が保たれるように調節されています。そんな中で、脂質異常症になると体内で脂質の流れがうまくコントロールできなくなり、血液中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)や中性脂肪(トリグリセライド)が高い状態、またはHDLコレステロール(善玉コレステロール)が低い状態になります。
脂質異常症のメカニズム
脂質異常症のほとんどは、生活習慣が原因となるとされています。それは、食べ過ぎ、お酒の飲み過ぎ、喫煙、運動不足などによる肥満などです。これらによって、本来ある脂質のバランスが崩れます。
さらに、血糖値が高いと肝臓は余分な糖を利用して中性脂肪を作るので、中性脂肪が高くなります。さらに、インスリンは血糖値を一定にする作用と脂肪を分解する働きがありますが、糖尿病でインスリンの分泌がうまくされないと中性脂肪も分解できず血液中の脂質が増えるので、脂質異常症につながります。また、中性脂肪が高い状態にあると、インスリンの血糖値を一定にする作用が効きにくくなるため、血糖値が高くなってしまうので、糖尿病の悪化の原因となります。
脂質代謝障害は中性脂肪が低いとどうなる?
通常であれば中性脂肪(トリグリセライド)が低いとHDLコレステロール(善玉コレステロール)は高くなる傾向があります。しかし、脂質代謝障害があると、中性脂肪が低いのにHDLコレステロールが低くなったり、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)が高くなったりします。
脂質代謝障害は中性脂肪が高いとどうなる?
中性脂肪(トリグリセライド)が高い状態にあると、HDLコレステロール(善玉コレステロール)が低くなったり、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)が高くなったりします。また、この状態が動脈硬化症となる危険が高いので注意する必要があります。
脂質の代謝異常
脂質の代謝異常だけでは全く自覚症状がありません。体内の血管に時間をかけてダメージを蓄積します。蓄積されたダメージによって、動脈が硬くなったり、血管壁にコレステロールが沈着するということが起こり、血液の流れが悪くなります。それが心臓に影響する血管に起こった場合は心筋梗塞や狭心症、脳内の血管で起こった場合は脳梗塞という危険な病気の原因となります。
脂質異常を治すには
脂質異常を治すには食事療法と運動療法、そして薬物療法があります。
- 食事療法
アルコールの摂取を控えて肉類の摂取を減らして食物繊維の摂取を増やすことで、必要以上のカロリーをとらないようにする療法です。
- 運動療法
ハードな運動よりは、毎日30分以上のウォーキングなどの有酸素運動が効果的とされています。
- 薬物療法
食事療法や運動療法などで改善が見られない場合は、薬物療法があります。
マグネシウムが糖尿病リスク・代謝障害リスクの低下に役立つ理由

マグネシウムが糖尿病リスク・代謝障害リスクの低下に役立つ理由としては、マグネシウムが糖尿病にも代謝障害にも関係のあるインスリンの働きを良くするからだと考えられます。
そんな中で、マグネシウム摂取量増加と糖尿病リスクの関係性を調べる実験がアメリカにおいておこなわれました。この実験内容としては、26~81歳の合計2,582名を対象として7年間、空腹時と食事後のグルコース、インスリン、インスリン感受性、インスリン抵抗性を計測するものでした。
糖尿病発症リスク「ー32%」
このアメリカの実験結果として、マグネシウムの摂取量が低い人と多い人を比較すると、摂取量が多い人は糖尿病発症リスクが「-32%」であるという結果が得られました。マグネシウムがインスリンの働きを良くしてくれたおかげで、糖尿病の発症リスクが下がったと考えられます。
代謝障害リスクが「ー37%」
また、このアメリカの実験結果では、マグネシウムの摂取量が低い人と多い人を比較すると、摂取量が多い人は代謝障害リスクが「-37%」であるという結果が得られました。代謝障害についても、マグネシウムを多く摂取している人はインスリンの働きが良いから、リスクが下がったと考えられます。
糖尿病原因
糖尿病の主な原因は、ストレス・食生活の乱れ・マグネシウム不足をきっかけとなって、インスリンの分泌が低下したり、インスリンがうまく働かなくなることです。
ストレス
ストレスが主な原因なんて、不思議だと思った方もいるかもしれません。しかし、ドイツのミュンヘンヘルムホルツセンターの調査によると、職場で強いプレッシャーを感じてストレスを抱えている人は、そうでない人に比べ、糖尿病を発症するリスクが45%上昇するという結果がでています。
食生活の乱れ
食べ過ぎたり、飲み過ぎたり、食事をとらなかったり、間食を多くとったり、食事のタイミングがばらばらであったり、偏食で栄養バランスが良くないといった、食生活の乱れは血糖値の上昇につながるため糖尿病の原因となります。
マグネシウム不足
マグネシウムが不足すると血糖値を下げるインスリンの分泌が低下したり、インスリンがうまく働かなくなって、血糖値が上昇してしまうため、糖尿病の原因となります。
糖尿病の原因であるストレスについては、趣味を見つける等して発散する方法を見つけておくべきです。食生活についても、栄養バランスを考えて3食とるようにすべきです。アルコール量は適量20gを超えないようにしましょう。そして、マグネシウムを意識してとるようにしましょう。食事でとるのが難しい場合は、簡単に摂取できて摂取量の計算がしやすいサプリメントなどで補って行くことが重要です。