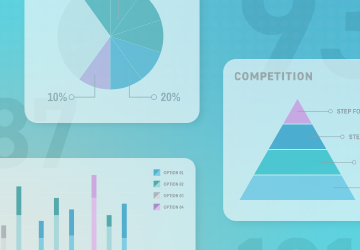マグネシウムは骨や歯の形成に必要!骨粗鬆症を予防するにはマグネシウムを飲もう
マグネシウムが骨や歯の形成に必要であることをご存じでしょうか?
骨と聞くとカルシウムが重要というイメージがありますが、マグネシウムも骨や歯の形成に欠かせない栄養素です。この記事では、マグネシウムの役割について詳しく説明します。
骨と歯の健康を支えるマグネシウムとは?

マグネシウムは骨や歯の健康に重要な役割を果たすミネラルであり、不足すると骨粗しょう症のリスクが高まったり、歯周病が悪化したりする可能性があります。
マグネシウムの基本的な役割とその重要性
マグネシウムは、骨や歯の形成に欠かせないミネラルで、健康維持に重要な役割を担っています。
- カルシウムの吸収や骨への沈着を助ける
- エナメル質の形成を助ける
- 骨密度の維持に役立つ
- 300種類以上の酵素の働きを助ける
- エネルギー産生や代謝をサポートする
- 細内外のミネラルバランスを調整する
マグネシウムが不足すると骨粗しょう症や歯のリスクが高まる可能性があるだけでなく、筋肉の痙攣やこむら返り、不眠、疲れやすさなどの体調不良が生じるほか、歯のエナメル質の形成に必要なカルシウムとの結びつきを通じて歯を強く保つ重要な役割も果たしています。
骨密度や弾力性に与える影響
マグネシウムは骨の構成要素の一つとして骨密度を保つ重要な役割を果たし、カルシウムと結びついて骨の構造を強化することで骨のミネラル量を適切に維持し、骨密度の低下や骨折のリスクを防ぎます。
体内のマグネシウムの50~60%は骨に存在し、そのうちの3分の2は骨の主成分であるハイドロキシアパタイトの結晶内に組み込まれ、残りの3分の1は結晶表面で複合体を形成しており、残りのマグネシウムは筋肉や軟部組織、細胞外液中に分布しています。
マグネシウムが不足すると、ハイドロキシアパタイト結晶の表面のマグネシウムが細胞外に流出し、それを補うために結晶内部のマグネシウムが表面に移動することで骨の結晶がスカスカになり、骨粗しょう症を引き起こします。
骨には硬さを提供するカルシウムとともにマグネシウムが含まれており、骨のコラーゲン繊維の強化や弾力性の維持に関与することで硬く丈夫でありながら適度な弾力性を持つ性質を保ちますが、マグネシウムが不足すると弾力性が失われて骨が硬くなりすぎ、衝撃に弱く骨折しやすくなる可能性があります。
骨粗鬆症の原因と予防法

骨粗しょう症は骨密度が低下して骨が脆くなり、軽い衝撃や転倒でも骨折しやすくなる病気です。
骨粗鬆症のメカニズムとリスク要因・予防法について以下に詳しく説明します。
骨粗鬆症のメカニズム:なぜ骨が脆くなるのか?
骨は骨芽細胞による新しい骨の形成と破骨細胞による古い骨の吸収を繰り返す新陳代謝(リモデリング)を行っています。
この新陳代謝のバランスが崩れて骨吸収が上回ると骨量が減少することによって骨粗しょう症を引き起こします。
加齢やホルモンバランスの変化によるリスク要因
加齢は骨粗しょう症の主要なリスク要因の一つとされています。
骨芽細胞の働きや骨の生成の低下や骨内部構造の弱化、さらにカルシウムやビタミンDの吸収能力の低下が進行することで骨の強度が低下して骨粗しょう症になりやすくなります。
ホルモンバランスの変化は男女ともに骨粗しょう症の発症に影響を与えますが、特に女性では閉経後に骨の分解を抑制するエストロゲンが急激に低下することで破骨細胞の活動が活発になり、骨吸収が増加して骨密度が急激に減少し、骨折リスクが高まります。
男性は加齢に伴いテストステロンが低下し、テストステロンが骨形成を促進しエストロゲンに変換されて骨の健康を支えるためその低下により骨密度が徐々に減少します。
骨粗しょう症の予防にはカルシウムの積極的な摂取が重要ですがカルシウムだけでなくマグネシウムの摂取も非常に重要です。
カルシウムが骨を硬くする一方でマグネシウムを摂ることで骨がさらに強く丈夫になるので、予防のためには若いうちからマグネシウム摂取を心掛けることが推奨されます。
カルシウムとマグネシウムの理想的なバランス

カルシウムとマグネシウムは、骨の健康や体内の様々な機能において相互に作用する重要なミネラルです。
マグネシウムがカルシウム吸収を助ける理由と、両者の適切な比率と健康維持への影響を以下で紹介していきます。
マグネシウムがカルシウム吸収を助ける理由
マグネシウムはカルシウムの吸収を助ける重要な役割を果たしています。
特にビタミンDの活性化や副甲状腺ホルモン(PTH)の調整に関与しており、ビタミンDが活性型に変換されることで小腸でのカルシウム吸収が促進されます。
マグネシウムが不足するとビタミンDが十分に活性化されずカルシウム吸収が低下するのでPTHの分泌や機能も低下してカルシウム代謝が乱れます。
両者の適切な比率と健康維持への影響
理想的なカルシウムとマグネシウムの比率は2:1で、この比率を保つことで骨や歯の健康、筋肉や神経の調節、心血管の健康を維持できます。
マグネシウム不足が引き起こす健康リスク

マグネシウム不足は約300種類以上の酵素反応に関与しています。
筋肉、神経、骨、心臓血管、エネルギー代謝に不可欠なミネラルであるため、体内のさまざまな機能に影響を与え、多くの健康リスクを引き起こす可能性があります。
骨粗鬆症以外の影響:筋肉の痙攣や心血管疾患
マグネシウムが不足すると骨粗しょう症だけでなく、特に筋肉の痙攣や心血管疾患に顕著な影響を引き起こす可能性があります。
筋肉の収縮はカルシウムによって促進され、弛緩はマグネシウムによって調節されており、マグネシウムが不足すると筋肉が過剰に収縮し、弛緩がうまく行われなくなり、カルシウムが過剰に筋細胞に流入して筋肉が異常に収縮することで痙攣が起こりやすくなります。
特にふくらはぎのこむら返りが典型的な症状となり、さらにマグネシウム不足は不整脈、高血圧、動脈硬化、心筋梗塞などの心血管系の健康問題を引き起こす可能性があります。
現代人の食生活とマグネシウム不足の現状
日本人のマグネシウム不足の原因として考えられるのは、「食生活の半欧米化」と「精製塩の過剰摂取」です。
戦後、日本人の伝統的な食生活が大きく変化し、大麦や雑穀などの全粒穀物の摂取が減少した結果、高脂肪・高カロリーの食事が増え、マグネシウムの摂取量が減少したと考えられます。
日本では1972年に塩田法が廃止されるまでは精製されていない粗塩が広く使用されており、粗塩にはマグネシウムをはじめとする多くのミネラルが含まれていました。
ところがライフスタイルの変化に伴い外食やファストフードの利用が増え日本人の塩分摂取量が増加し、塩分の過剰摂取により体内からのマグネシウムの排泄が増加することでマグネシウム不足がさらに深刻化を増しています。
骨粗鬆症予防のためのライフスタイル改善

骨粗鬆症を予防するためには、日常生活の中で栄養、運動、生活習慣などのバランスを整えることが重要です。
以下に、骨粗鬆症予防のためのライフスタイル改善策を具体的に説明します。
バランスの取れた食事と適度な運動
骨粗鬆症予防のためには、骨を強くする栄養素を含むバランスの取れた食事と、骨密度を維持するための適度な運動を組み合わせることが重要です。
骨を健康に保つための栄養素と、それを含む食品を紹介します。
- カルシウムは乳製品・大豆製品・魚介類・海藻類に含まれます。野菜では、小松菜に豊富に含まれます。
- ビタミンDはサケ、サバ、イワシの魚、卵黄、きのこ(特に干しシイタケ)に含まれます。
- マグネシウムはナッツ類・かぼちゃの種等の種子類・全粒穀物、海藻類に含まれます。
- タンパク質は鶏肉、魚、大豆製品、乳製品、卵に含まれます。
運動は骨を強化するだけでなく骨密度を高めるために不可欠であり、骨粗鬆症予防にはウォーキングのような有酸素運動、スクワットや腕立て伏せの筋力トレーニング、ヨガのようなバランス運動が効果的です。
週に3~5日以上、1日30分~1時間程度行うことがポイントですが、転倒のリスクを避けるため無理をせず、高齢者や体力に自信のない人は医師に相談して適切な運動を選ぶことが安全のために重要です。
ビタミンDの役割と日光浴の重要性
ビタミンDは、カルシウムの吸収を助け、骨形成や骨密度の維持に不可欠な栄養素です。
日光浴は体内でのビタミンD合成を促進し骨粗鬆症予防に重要ですが、現代生活では不足しがちなので、意識的に外出したり、食事やサプリメントで補うことが大切です。
骨と歯を守るためのマグネシウム習慣
適度な運動でマグネシウムの代謝をサポートしてくれるので必要に応じてサプリメントを活用することで健康を長く保つことができます。
マグネシウム習慣を身につけて、大切な骨と歯をしっかり守りましょう!