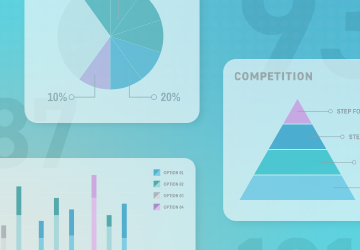1日のマグネシウム摂取量が糖尿病リスクを軽減させる理由・効果を詳しく解説
マグネシウムに1日に摂取する”推奨量”が定められている理由を解説します
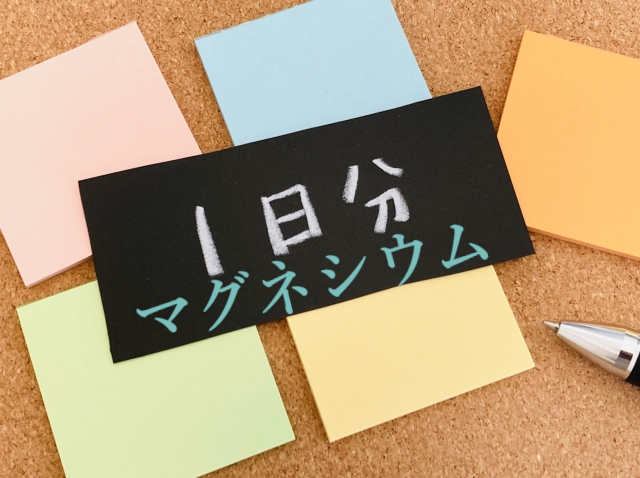
マグネシウムを意識的に摂取していますか?健康に生活していく為に、カルシウムやビタミンに代表される様々な栄養素には1日で摂取する”推奨量”があります。マグネシウムも同様に”推奨量”があり、その理由を解説していきます。
1日に必要なマグネシウムの摂取基準・推奨量
厚生労働省が策定した日本人の食事摂取基準(2020年版)によると、1日に必要なマグネシウムの”推奨量”は18~29歳の男性は340mg女性は270mg、30~64歳の男性は370mg女性は290mgとなっています。その推奨量に対してどれぐらい摂取できているのでしょうか。
国民健康・栄養調査結果の概要(令和元年)によると、男女計1人当たり平均値247mgとなっており、推奨量に対して少ないことがわかります。
現代人のマグネシウム摂取量が少ない理由
マグネシウムの摂取量が少ない決定的な理由は「食の欧米化」にあります。
現代人は、日本型食生活といえるマグネシウム含有量の高い魚介類、穀物類、野菜類などの食事から、マグネシウム含有量の低い肉類を中心とした食事に変化したことでマグネシウムの摂取量が低くなっています。
マグネシウムの効果はヒトの生命活動をサポート
マグネシウムの研究でマグネシウムは細胞の生命維持に深く関わっていることが分かっています。
マグネシウムはタンパク質合成、血糖コントロールや血圧調整、筋肉や神経の機能などを制御する300以上の酵素を活性化・維持する働きがあり、ヒトの生命活動をサポートしています。
現代人こそ摂取すべき!マグネシウムと糖尿病の関係を詳しく解説します
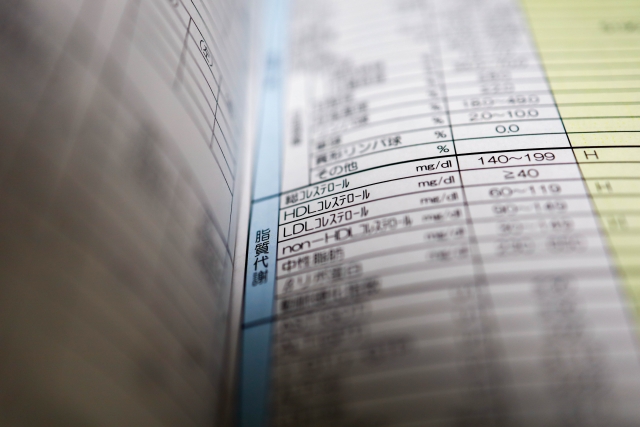
糖尿病はインスリンというホルモンの不足や作用低下が原因で、血糖値の上昇を抑える働きが低下することで高血糖が慢性的に続く病気で、網膜症・腎症・神経障害の三大合併症をしばしば伴います。また、マグネシウム不足が糖尿病のリスクに関係があることが近年明らかにされています。
マグネシウムと血糖値の関係を詳しく解説
マグネシウムは酵素を助ける役割がありますが、糖代謝の際にもしっかり働いています。また、糖を細胞内に取り込む際にもマグネシウムが必要です。マグネシウムが足りなくなると血液中から糖を取り込めなくなって、血糖値の高い状態が続いてしまうので肥満や糖尿病にもつながります。
マグネシウムとインスリンの関係を詳しく解説
マグネシウムを摂取すると血糖値が下がるメカニズムは、インスリンの抵抗性を低下(感受性を良化)させることにあります。逆に言うとマグネシウムが不足するとインスリンの抵抗性が高まり(感受性が悪化)し、血糖値が上昇してしまいます。
このようにマグネシウムはインスリンの働きに密接な関係があるといえます。
インスリン感受性とは
インスリン作用の具合(効き目)の呼び方としてインスリン感受性という言葉が使われます。
インスリンの作用が弱まっている状態をインスリン感受性の低下(悪化)と呼び、逆に強くなっている場合はインスリン感受性の上昇(良化)と呼びます。
インスリン抵抗性とは
インスリン抵抗性とは、一定量のインスリンが血糖値を下げる能力の低下を表す指標です。
インスリン抵抗性が高いということは、血糖値が上がりやすく糖尿病のリスクが高まっていることであり、インスリンの抵抗性が高くなることでインスリンの作用不足を招きます。
マグネシウムがインスリン感受性を改善する理由
マグネシウムがインスリン抵抗性(感受性)を改善する理由は、マグネシウムはインスリンの働きをサポートする役割を持っているからです。つまり、体で必要なマグネシウムを必要な分だけ摂取するとインスリンが正常に働いてくれることでインスリン感受性が改善されるといえます。
”成人病”と言われる糖尿病の患者数

世界の糖尿病人口(糖尿病患者数)は大きく増加傾向にあります。
その糖尿病には1型糖尿病と2型糖尿病があります。1型はインスリン依存型と呼ばれ、インスリン分泌細胞が壊されるもので、インスリンが不足するためインスリンの自己注射が必要なタイプです。
2型糖尿病はインスリン非依存型と呼ばれ、遺伝によるものや過食や運動不足などの生活習慣が重なることで発症するタイプです。
一型糖尿病の患者数
厚生労働省の発表によると、国内の患者数は10-14万人といわれています。
二型糖尿病の患者数
2型に疾患している人の方が多く、国内ではその疑いがある人も加えると1千万人以上と推定されています。
糖尿病の原因は大きく4つ

糖尿病にかからないようにしていくためには、原因を知ることが大切です。
大きく4つの原因があるので健康な体を維持するためにも普段から対策しましょう。
ストレス
ストレスは、何かの刺激を受けたり感じたりした時に発生する緊張状態のことです。
刺激には、騒音や天気などの環境的問題、病気になったり睡眠不足などの身体的問題、不安を感じたり悩みを抱えたりなど心の問題、そして人間関係がよくない、仕事が忙しいというような社会的問題といった様々な問題が存在しています。つまり、日常で起こる変化が、ストレスの原因になるのです。
ストレスが身体や心にかかると血糖値が上がるホルモン(グルカゴン、コルチゾール、成長ホルモン等)が分泌される一方で、インスリン抵抗性が高まり、インスリン抵抗性が高まることで血糖値が上がりやすくなるため糖尿病のリスクが高まります。
肥満
肥満になると、インスリンのはたらきが悪くなるため、すい臓はインスリンをたくさん作ろうとはたらいて体内のインスリン量が増加します。その後、すい臓が付かれることで機能が低下してしまい、血糖値が上がることが糖尿病の原因となります。
運動不足
運動をするとエネルギーを筋肉で消費します。
食後に行う運動は、インスリンの感受性が良化し食後の血糖値の上昇を抑えて、血糖のコンロールの改善が期待されます。運動不足とは、この有益な機会を失うことになるため糖尿病の原因となります。
暴飲暴食
暴飲暴食をすると、食事の際にブドウ糖を処理しなければならず、大量のインスリンをすい臓は分泌するため疲れてしまいます。疲れてしまうことで機能が低下してしまうことから、血糖値が上がって糖尿病の原因となります。
あなたは大丈夫?日常に潜む糖尿病の”リスク”を詳しく解説

ストレス・肥満・運動不足・暴飲暴食が糖尿病の原因であるということはご理解いただけたと思います。
次にあげる行動に当てはまる方は注意が必要です。
- 毎日、帰宅してからお酒を飲む
- スナック菓子等をおつまみに食べながら動画を見るのが趣味
- 毎日2時間はお酒を飲みながらおつまみを食べ、運動せずにダラダラと過ごして寝る
- 太ってきたという自覚はあるが、特に体の不調を感じないのでやり過ごす
このような生活に当てはまる場合は糖尿病のリスクがあるといえるので食生活や生活習慣を見直し、意識的に改善することが大切です。
糖尿病を招く様々なリスク
「生活習慣病」という言葉を聞いたことがあると思います。
これは、食習慣・運動習慣・休養・喫煙・飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する症候群、と定義されています。食事などの生活習慣から様々な糖尿病に対するリスクがありますので、生活習慣から見直していくことが重要です。
手軽に糖尿病対策・リスク軽減するならマグネシウムがおすすめ

生活習慣病は糖尿病につながりますが、長年の生活習慣を変えるのはなかなか難しいというのが実際のところではないでしょうか。そこで、おすすめしたいのがマグネシウムの摂取です。
食事の中で取り入れることもできますが、継続してマグネシウム含有量の多いものを選んで食べるというのは、忙しい方々にとっては難しいかもしれません。
サプリメントであれば手軽に摂取できて糖尿病のリスク低が期待できるのでおすすめです。
まとめ

生活習慣に起因するためなかなか意識しないと改善するのが難しい病気ですが、糖尿病は網膜症・腎症・神経障害といった三大合併症を伴う病気で恐ろしい病気です。また、動脈硬化が進行して心臓病や脳卒中のリスクも高まります。
糖尿病対策にはストレスをため込まない、カロリーコントロール等で太らないようにする、適度に運動をする、飲みすぎ・食べ過ぎをしないことが大切です。
マグネシウムの摂取を意識的に行い、糖尿病のリスクに備えましょう。