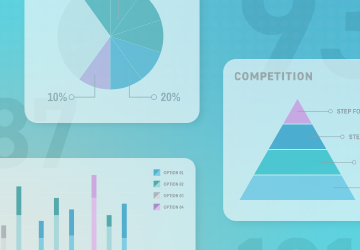月経前症候群(pms)とはどんな病気?症状・原因・予防方や治療方を詳しく解説
月経前症候群(pms)とはいったいどのような症状でしょうか。
月経の始まる数日前から始まり、月経が始まると軽減する、身体的および精神的な症状の総称を指します。女性特有の月経は、その症状によって体調の変化が著しく辛いでしょう。
この記事では、月経前症候群の症状や原因、治療法やなりやすい人等を詳しく解説します。
月経前症候群(pms)の症状

月経前症候群(pms、Premenstrual Syndrome)とはいったいどのような症状を指すでしょうか。
ここでは、月経前症候群の色々な症状について身体的、精神的な症状を細かく詳しく見ていきましょう。
精神不安
月経前症候群の一部として現れる精神不安は、多くの女性にとって悩ましい問題です。精神不安は、ホルモンの変動や神経伝達物質の変化が関与していると考えられています。
- ホルモンの変動: エストロゲンやプロゲステロンのレベルが月経周期に伴って変動し、これが気分や感情に影響を与えます。
- 神経伝達物質の変化: セロトニンやドーパミンなどの脳内の化学物質のバランスが変わり、これが不安感や抑うつ感を引き起こすことがあります。
- ストレス: 月経前症候群自体がストレスの原因となり、そのストレスがさらに不安感を悪化させることがあります。
精神不安は多くの女性が経験する共通の問題ですが、適切な対処法を見つけることで症状を軽減することが可能であり、ライフスタイルの改善やストレス管理、場合によっては医学的アプローチを取り入れることで、より快適な日常生活を送れるでしょう。
イライラ
イライラもホルモンの変動や神経伝達物質の変化、ストレスによって引き起こされる場合が多く、こちらもエストロゲンやプロゲステロンのレベルが月経周期に伴って急激に変化する事や、セロトニンやドーパミンなどの脳内化学物質のバランスが崩れることで、感情の調整が難しくなり、イライラ感が増します。
また、日常生活のストレスや月経前症候群そのものが引き起こす身体的な不快感が、イライラを悪化させることがあります。
重度の不快症状
月経前症候群の中でも特に重度の不快症状は、日常生活に大きな影響を及ぼすことがあります。
重度の月経前症候群の一形態として、月経前不快気分障害(PMDD:Premenstrual Dysphoric Disorder)と呼ばれる診断が存在します。
以下に、重度の月経前症候群およびPMDDの症状を列挙します。
身体的症状
- 著しい乳房の痛みや張り
- 手足のひどいむくみ
- 激しい腹痛や下腹部の膨満感
- 激しい頭痛
- 極度の疲労感
- 胃腸の不調(吐き気、便秘、下痢)
精神的・感情的症状
- 重度のイライラや怒り
- 極度の不安や緊張感
- 深い抑うつ感や絶望感
- 体重増加
- 筋肉痛や関節痛
- 集中力の著しい低下
- 感情の激しい起伏
- 自殺念慮を含む深刻な抑うつ
- 過度の睡眠障害(不眠または過眠)
- 対人関係の問題(孤立感、関係の悪化)
食欲不振
月経前症候群の症状の一つに食欲不振があります。
食欲不振が続くと、栄養不足やエネルギー不足につながり、全体的な健康状態や体力に影響を与える可能性もあることと、月経前症候群期間中に栄養不足になると、他の月経前症候群症状が悪化することもありますので注意が必要です。
頭痛・吐き気
月経前症候群による頭痛や吐き気は、多くの女性が経験する一般的な症状であり、症状の発生は月経の数日前から始まり、月経が始まると軽減します。
集中力の低下
月経前症候群に伴う集中力の低下は、仕事や学業、日常生活に影響を及ぼすことがあります。
月経前症候群の期間中に集中力が低下する原因は、ホルモンの変動、精神的なストレス、身体的な不快感などが複合的に影響していると考えられています。
月経前症候群(pms)の原因
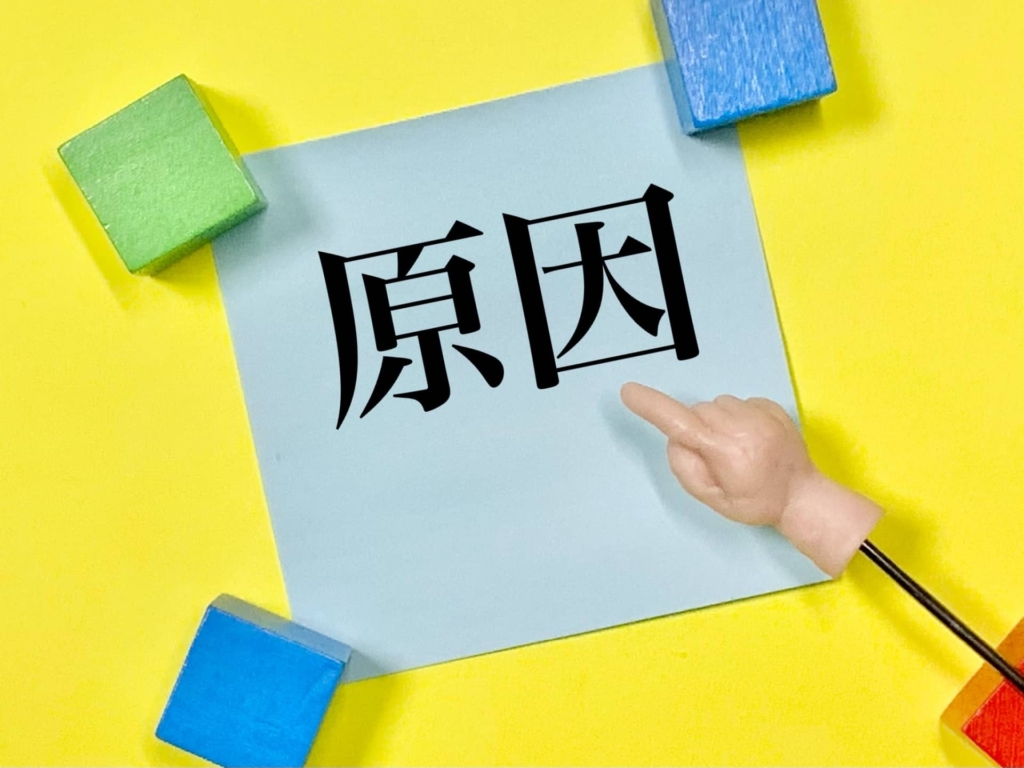
では、月経前症候群の原因はどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、月経周期に関しての女性ホルモンの乱れや黄体期について、さらには加齢、栄養不足について詳しく解説します。
女性ホルモンの乱れ
女性ホルモンの乱れは、月経周期に関連しています。
女性の月経周期は、エストロゲンとプロゲステロンという2つの主要なホルモンによって調整され、これらのホルモンのレベルは、月経周期の異なる段階で変動します。
月経の直前にプロゲステロンのレベルが急激に低下することで、月経前症候群の症状が引き起こされます。
黄体期
黄体期というのは、月経周期の14日目から28日目にあたり、排卵後から次の月経が始まるまでの期間を指します。この時期に、ホルモンの変動がさまざまな身体的および精神的な症状を引き起こすことがあります。
- プロゲステロンの増加:
- 排卵後、黄体から分泌されるプロゲステロンが急激に増加します。プロゲステロンは子宮内膜を厚くし、受精卵が着床するのを助けます。
- エストロゲンの変動:
- 排卵後、エストロゲンのレベルも一時的に増加しますが、その後徐々に減少します。
- ホルモンの低下:
- 妊娠が成立しなかった場合、黄体期の終わりに向かってプロゲステロンとエストロゲンのレベルが急激に低下します。この急激なホルモンの低下が、月経前症候群の症状の主な原因と考えられています。
加齢
思春期から20代にかけては、ホルモンのバランスがまだ安定していないため、月経前症候群の症状が重い場合があります。月経周期も不規則なことが多く、月経前症候群の症状が予測しにくいことがあります。
30代に入ると、ホルモンのバランスが比較的安定することが多いですが、ストレスやライフスタイルの変化により、月経前症候群の症状が強くなることがあります。また、この年代は多くの女性が仕事や家庭での責任を抱えているため、ストレスが影響を与えることがあります。
40代になると、プレ更年期(更年期の前段階)に入り、エストロゲンとプロゲステロンのレベルが変動しやすくなります。この変動が月経前症候群の症状を悪化させ月経周期が短くなったり、不規則になったりすることがあり、これが症状を強化する原因となります。
閉経に近づくにつれて、症状が更年期症状と重なることが多くなります。
ホットフラッシュ、夜間の発汗、不眠、気分の変動などが加わることで、月経前症候群の症状が複雑になることがあります。
栄養不足
栄養不足は、体内のホルモンバランスや神経伝達物質の機能に影響を与え、症状を悪化させる可能性があります。特にカルシウムやマグネシウム、ビタミンの中でもB6やDに関しては栄養素が不足すると、月経前症候群が顕著になることがあります。
月経前症候群(pms)の治療法

月経前症候群の治療法は、症状の重さや種類によって異なりますが、主な所では生活習慣の改善、薬物療法、ホルモン療法、心理療法など、多岐にわたります。
ここでは治療法で大事な事を詳しく解説します。
婦人科の受診
日常生活に支障をきたしている場合、婦人科の受診が重要です。婦人科医は、症状の原因を特定し、適切な治療法を提案してくれる専門家ですので、我慢せずに婦人科を受診しましょう。
以下にその流れを解説します。
婦人科での診察の流れ
- 問診
- 症状の詳細、月経周期、過去の病歴、家族歴について質問されます。
- 身体診察
- 必要に応じて、身体診察や内診します。
- 検査
- 血液検査やホルモン検査が行われることがあります。また、超音波検査などの画像診断が必要な場合もあります。
- 治療計画の立案
- 診断結果に基づいて、個別の治療計画が立てられます。薬物療法、ホルモン療法、ライフスタイルの改善など、さまざまなアプローチが考慮されます。
薬物療法
月経前症候群では薬物療法することがあります。薬物療法については、症状や重さによって種類が異なりますので、知識を身につけて自分の症状を理解しましょう。
主には、鎮痛薬、抗うつ剤、利尿薬、サプリメント、ゴナドトロピン放出ホルモン(GnRH)アゴニストが一般的です。
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)
- 代表薬: イブプロフェン、ナプロキセン
- 効果: 頭痛、筋肉痛、腹痛などの痛みを軽減します。
- 使用方法: 痛みが現れ始めたら、指示された用量で服用します。
選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)
- 代表薬: フルオキセチン(プロザック)、セルトラリン(ゾロフト)、パロキセチン(パキシル)
- 効果: 重度の月経前症候群やPMDD(月経前不快気分障害)の気分の変動、イライラ、不安、抑うつ感を軽減します。
- 使用方法: 毎日定期的に服用する方法と、月経前の2週間だけ服用する方法があります。医師の指示に従います。
- 代表薬: デュロキセチン(シンバルタ)、ベンラファキシン(エフェクサー)
- 効果: SSRIと同様に、気分の変動や不安感を軽減します。
ホルモン療法薬
ホルモン療法については以下の療法薬を使って実施します。
経口避妊薬
- 代表薬: 複数のブランドがありますが、エストロゲンとプロゲステロンの組み合わせ薬が一般的です。
- 効果: ホルモンバランスを調整し、月経前症候群の身体的および精神的症状を軽減します。
- 使用方法: 通常、21日間服用し、7日間休薬するサイクルで使用されます。
黄体ホルモン(プロゲステロン)
- 効果: 月経前症候群の症状を軽減するために、黄体ホルモンが補充されることがあります。
- 使用方法: 医師の指示に従って、特定の日に服用します。
漢方
漢方薬は、月経前症候群の治療においても広く使用されています。漢方薬は、体全体のバランスを整えることを目的とし、個々の症状や体質に合わせた治療を実施します。
加味逍遙散(かみしょうようさん)
- 効果: 精神的な不安、イライラ、抑うつ感、ホットフラッシュ、冷え性などに有効です。
- 構成生薬: 当帰、芍薬、茯苓、柴胡、甘草、薄荷、牡丹皮、山梔子など
- 適応: ストレスやホルモンバランスの乱れによる月経前症候群に対して使用されます。
桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)
- 効果: 血行を促進し、瘀血(おけつ:血液の滞り)を改善することで、月経痛、頭痛、肩こり、冷え性などを軽減します。
- 構成生薬: 桂皮、茯苓、牡丹皮、桃仁、芍薬
- 適応: 血行不良や瘀血が原因と考えられる月経前症候群に対して使用されます。
当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)
- 効果: 血行を促進し、貧血、冷え性、むくみ、疲労感などを改善します。
- 構成生薬: 当帰、芍薬、川芎、茯苓、白朮、沢瀉
- 適応: 冷え性や血行不良、むくみが原因と考えられる月経前症候群に対して使用されます。
抑肝散(よくかんさん)
- 効果: 精神的な緊張、不安、イライラ、抑うつ感を軽減します。
- 構成生薬: 当帰、芍薬、茯苓、甘草、柴胡、釣藤鈎
- 適応: 精神的なストレスや緊張が原因と考えられる月経前症候群に対して使用されます。
半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)
- 効果: 気分の変動、不安感、胸のつかえ感、咽喉頭異常感を改善します。
- 構成生薬: 半夏、厚朴、茯苓、生姜、蘇葉
- 適応: 精神的な不安や気分の変動が原因と考えられる月経前症候群に対して使用されます。
薬に頼らない治療
月経前症候群(PMS)の治療には、薬物療法以外にもさまざまな方法がありますが特に、栄養管理、運動、ストレス管理などを通じて症状を緩和することが一般的な治療目的となります。
運動は主に有酸素運動、ヨガやピラティス等を実施すると体調改善に大いに役立ちます。
ウォーキング、ジョギング、サイクリング等これらの運動はエンドルフィンの分泌を促し、気分を改善するため、週に少なくとも3〜4回、30分以上の運動を目指しましょう。
リラクゼーションとストレッチ等ヨガやピラティスはストレスの軽減やリラクゼーションに効果的ですので、深呼吸や瞑想と組み合わせることで、精神的な安定を図れます。
生活環境の改善
生活環境を改善することは、月経前症候群に有効です。特に食生活の見直しは体のホルモンバランスを整え、重い症状を改善することに役立ちます。
栄養バランスの取れた食事
- カルシウムとマグネシウム: これらのミネラルはPMS症状の軽減に役立ちます。乳製品、緑黄色野菜、ナッツ、種子類などを多く摂取しましょう。
- ビタミンB6: 鶏肉、魚、バナナ、ほうれん草などの食品に含まれるビタミンB6は、気分の変動を軽減するのに効果的です。
- ビタミンD: 日光浴やビタミンD強化食品、脂肪の多い魚を通じてビタミンDを摂取することが推奨されます。
- オメガ3脂肪酸: 魚油、亜麻仁油、チアシードなどは、抗炎症作用があり、PMS症状の軽減に役立ちます。
カフェインとアルコールの制限
- カフェイン: コーヒーや紅茶、エナジードリンクなどのカフェイン含有飲料を控えることで、イライラや不安感を軽減できます。
- アルコール: アルコールの摂取を控えることで、睡眠の質や全体的な体調が改善されることがあります。
月経前症候群(pms)になりやすい人

月経前症候群になりやすい人には、いくつか共通する特徴やリスクファクターがあります。
発症リスクを高める要因には、遺伝的、環境的、心理的、ホルモン的な要因が関与していますが、ここではそれぞれなりやすい年齢や生活習慣、食習慣について詳しく解説します。
月経前症候群(pms)になりやすい年齢
月経前症候群は、特に30代から40代の女性に多く見られますが、思春期以降、つまり月経が始まった後であれば、どの年齢でも発症する可能性があります。
思春期から20代
- 思春期: 月経が始まったばかりの若い女性でも月経前症候群を経験することがありますが、ホルモンバランスが安定するまで時間がかかるため、初めのうちは症状が軽いでしょう。
- 20代: 20代になると、ホルモンの変動が安定してくるため、月経前症候群が現れることが増えてきます。しかし、非常に重篤になることは少ないでしょう。
30代から40代
- 30代: 多くの女性にとって、この年代は月経前症候群の症状が最も顕著になる時期です。妊娠や出産、育児、仕事のストレスなど、生活の変化が多い時期であることも影響します。
- 40代: この年代では、閉経に向けたホルモンの変動が始まり、月経前症候群が悪化することがあります。特に、更年期前(プレメノポーズ)にはホルモンバランスが不安定になりやすく、症状が強くなります。
更年期以降
- 更年期: 更年期(通常は45歳から55歳の間)には、月経周期が不規則になり、ホルモンの変動が大きくなるため、一部の女性は月経前症候群のような症状を経験することがあります。
- 閉経後: 閉経後は月経が停止するため、月経前症候群の症状自体は無くなりますが、ホルモンの変動に伴う更年期症状が続くことがあります。
月経前症候群(pms)になりやすい生活習慣
生活習慣の乱れは月経前症候群を誘発してしまうほど問題があります。
主な生活習慣の問題として「運動不足」「高ストレス環境」「不規則な睡眠習慣」「喫煙」「体重の管理」「精神的な健康状態」が挙げられます。これらの習慣を改善することで、月経前症候群の症状を軽減することが可能となりますので、適度な運動、効果的なストレス管理、十分な睡眠を心掛けることが重要です。
また、自己管理が難しい場合は、専門家のアドバイスを受けることも有効です。
月経前症候群(pms)になりやすい食習慣
不健康な食生活は、月経前症候群になりやすくそれ以外の病気に対しても免疫力が低下してしまうなどあまり良い事はありません。
例えば以下のような食習慣の場合は特に注意が必要です。
高脂肪・高糖質の食事
- ジャンクフードや加工食品: これらの食品はホルモンバランスを乱し、月経前症候群の症状を悪化させる可能性があります。
- 精製糖: ケーキやクッキー、ソーダなどの高糖質食品は血糖値の急上昇と急降下を引き起こし、イライラや疲労感を増幅させます。
栄養不足
- ビタミンやミネラルの欠如: 特にカルシウム、マグネシウム、ビタミンB6などが不足すると、月経前症候群の症状が悪化することがあります。
カフェインとアルコールの過剰摂取
- カフェイン: 過剰なカフェイン摂取は不安感やイライラを増加させることがあります。
- アルコール: アルコールはホルモンバランスを乱し、月経前症候群の症状を悪化させる可能性があります。
月経前症候群(pms)の予防法

月経前症候群の予防には、生活習慣の改善が大きな役割を担いますので、症状を軽減するための具体的な方法を紹介します。
日頃からのセルフケア
日頃からのセルフケアとして、バランスの取れた食事、定期的な運動、効果的なストレス管理、十分な睡眠、補完代替療法などを取り入れることが、月経前症候群の症状を予防し軽減するために重要です。これらの方法を組み合わせて実践することで、ホルモンバランスを整え、生活の質を向上できます。
特に定期的な運動やストレス管理は重要となりますので、日頃から有酸素運動を実施したり、深呼吸を実施してセルフケアを意識しましょう。
生活習慣の見直し
生活習慣の中でも特に睡眠と喫煙には気を付けて過ごすようにしましょう。
睡眠は十分な睡眠時間をとるように心がけ、7~8時間の質の良い睡眠を確保できるようにし、毎日同じ時間に寝起きする習慣をつけましょう。
喫煙はホルモンバランスに悪影響を及ぼし、月経前症候群を悪化させる可能性がありますので、禁煙を視野に入れて生活する事を考えましょう。
リラックスと休息
リラックスと休息にはとても重要な要素も含まれています。
補完代替療法や、リラクゼーションには以下のようなものがありますので取り入れてみてはいかがでしょうか。
瞑想と深呼吸
- 瞑想: 毎日数分間瞑想することで、ストレスの軽減や精神的なリラクゼーションが得られます。
- 深呼吸: ゆっくりと深い呼吸することで、心を落ち着かせる効果があります。
趣味やリラクゼーションの時間
- リラクゼーション: 自分の好きな活動や趣味に時間を割くことで、リフレッシュし、精神的な安定を図れます。
- 自然の中で過ごす: 自然の中で過ごす時間を増やすことも、ストレスの軽減に役立ちます。
アロマセラピー
- 精油: ラベンダー、カモミール、ベルガモットなどの精油を用いたアロマセラピーは、リラクゼーションやストレス軽減に効果的です。
マッサージ
- リラクゼーションマッサージ: マッサージを受けることで、筋肉の緊張をほぐし、リラクゼーションを促進します。
食生活の改善
食生活の改善は全ての病気に有効なので、積極的に取り入れるように心がけましょう。
ここでは月経前症候群に必要な栄養素の関係を詳しく解説していきます。
月経前症候群(pms)とミネラルの関係
ミネラルは体内のさまざまな生理機能をサポートしており、月経前症候群の症状軽減にも大きな役割を果たすとされています。
1. カルシウムの役割
- 骨の健康: カルシウムは骨や歯の構造を維持するために必要です。
- 筋肉機能: 筋肉の収縮と弛緩に関与します。
- 神経伝達: 神経インパルスの伝達を助けます。
月経前症候群との関係
- 症状軽減: 研究によると、カルシウムの補給はPMSの症状、特に気分の変動、イライラ、疲労感、食欲変動を軽減することが示されています。
- 推奨摂取量: 成人女性の場合、1日あたり約1000〜1200mgのカルシウムを摂取することが推奨されています。
2. 鉄の役割
- 酸素運搬: 赤血球のヘモグロビンに結合して酸素を運びます。
- エネルギー代謝: 酸素を利用したエネルギー生成に関与します。
月経前症候群との関係
- 疲労感の軽減: 鉄分不足は疲労感や集中力の低下を引き起こす可能性があり、PMSの症状を悪化させることがあります。
3. 亜鉛の役割
- 免疫機能: 免疫細胞の正常な機能をサポートします。
- 細胞分裂: 細胞の成長と修復に必要です。
月経前症候群との関係
- 情緒の安定: 亜鉛は神経伝達物質の調整に関与し、情緒の安定に寄与します。PMSの症状軽減にも役立つ可能性があります。
月経前症候群(pms)とマグネシウムの関係
マグネシウムは体内の多くの生理的プロセスに関与しており、PMSの症状軽減にも重要な役割を担っています。
マグネシウムの役割
- エネルギー生成: 細胞のエネルギー生成に関与する酵素の補因子として働きます。
- 筋肉と神経の機能: 筋肉の収縮と弛緩、神経伝達の調整に必要です。
- 骨の健康: カルシウムとともに骨の形成と維持に関与します。
- ホルモンの調整: 女性ホルモンのバランスを保つ役割も担います。
月経前症候群との関係
- 頭痛: マグネシウムは血管の拡張と収縮を調整する役割を担い、頭痛の軽減に寄与します。
- 腹部膨満感: マグネシウムは体内の水分バランスを調整するため、むくみや腹部膨満感の軽減に役立ちます。
- イライラや不安感: 神経伝達物質の調整により、気分の安定や不安感の軽減が期待されます。
- 筋肉の痛みやこむら返り: 筋肉の収縮と弛緩を助けることで、痛みやこむら返りの軽減に効果があります。
マグネシウムサプリメントの摂取が月経前症候群症状の軽減に効果的です。
推奨される摂取量は、成人女性で1日あたり約310〜320mgですが、個々のニーズや症状に応じて、医師や栄養士と相談して適切な量を決定することが重要です。
以下の食品はマグネシウムを豊富に含んでいます:
- 緑黄色野菜: ほうれん草、ケールなど
- ナッツと種子: アーモンド、カシューナッツ、かぼちゃの種
- 全粒穀物: 全粒パン、玄米、オートミール
- 豆類: 黒豆、ひよこ豆、レンズ豆
- 魚介類: サーモン、マグロ
月経前症候群の症状軽減には、カルシウムやマグネシウムを含むミネラルが重要な役割を担います。
バランスの取れた食事や適切なサプリメントの利用を通じて、これらのミネラルを十分に摂取することが、月経前症候群の症状を緩和し、全体的な健康を維持するために有益です。
月経前症候群(pms)の症状・原因・予防方や治療方まとめ
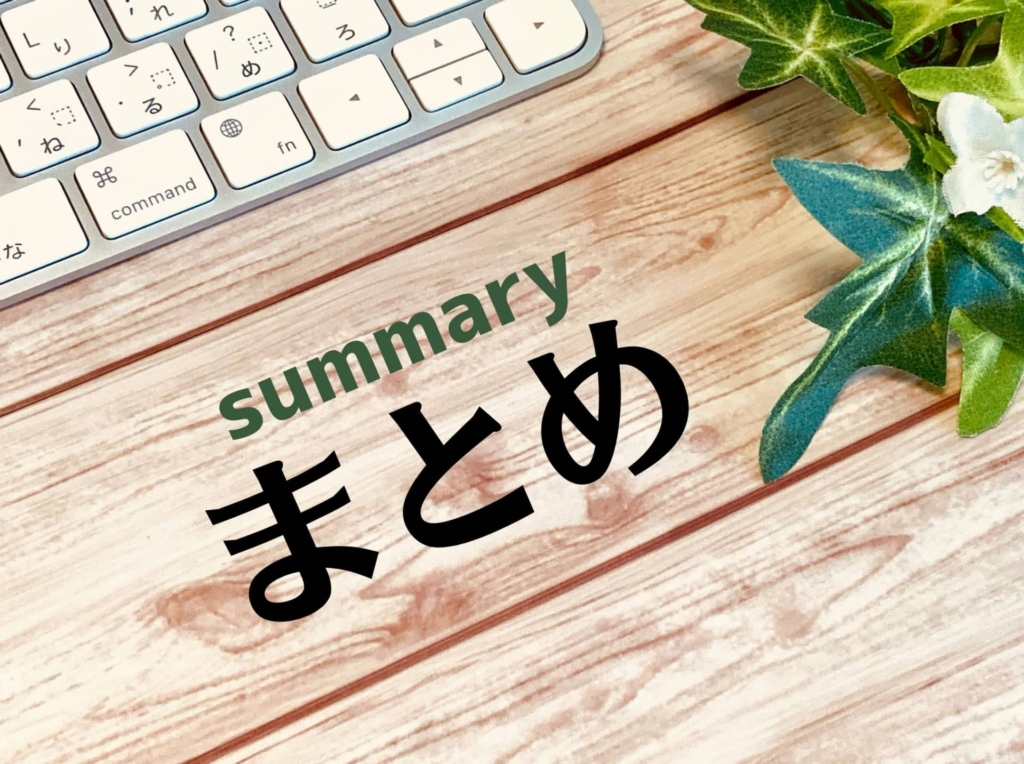
月経前症候群は、月経の始まる数日前から始まる身体的、精神的な症状の総称を指します。症状としては精神不安、イライラ、重度の不快症状、食欲不振、頭痛吐き気、集中力の低下があります。
原因として主に挙げられるのは、女性ホルモンの乱れが起因しているとされており、月経周期に関連する女性ホルモンの変化が大きな要因であると言われています。また、加齢についても30~40代にかけて特に症状が強く出てしまう傾向があります。
治療方法は、まず婦人科を受診して現在の症状を医師に伝えることが非常に重要です。自己治癒方法としては生活習慣の改善や食生活の改善、適度な運動やリラクゼーションを取り入れることで症状の改善が見込めます。
月経前症候群にはミネラルの要素を多く取り入れることが非常に重要であると研究結果が出ています。カルシウムやマグネシウムを積極的に摂取して生理機能の改善に努めることが、症状の軽減につながる第一歩になるでしょう。